2025.11.17コラム
口から始まる健康経営:歯科衛生士が伝えたい企業歯科健診の価値
目次
はじめに

近年、企業が従業員の「健康経営」に力を入れる流れの中で、歯科健診の重要性が注目されています。健康診断といえば血圧や血液検査などが一般的ですが、実は「口の中」こそが健康の入り口。歯科衛生士として企業健診に携わる中で感じるのは、口腔の状態が働く人の心身のコンディションに密接に関係しているという事実です。
たとえば、歯周病が進行している人ほど疲れやすく、集中力が低下しているケースが多い。逆に、口の中が整っている人は表情も明るく、会話のトーンも前向き。これは偶然ではありません。歯科衛生士の立場から見ても、職場での歯科健診は「働く人の笑顔を守る」ための第一歩だと感じます。
本コラムでは、そんな企業歯科健診の現場を歯科衛生士の視点で深掘りし、その意義と可能性をお伝えします。
企業歯科健診とは?

企業歯科健診とは、企業が従業員に対して実施する口腔の健康チェックのことです。一般的な健康診断では口の中をじっくり見る機会はほとんどありません。しかし、実際には歯周病やむし歯は「自覚症状が出にくい」ため、健診での早期発見がとても重要なのです。
健診内容は、歯周ポケットの測定、歯石・プラークの有無、むし歯のチェック、口臭・噛み合わせの確認など多岐にわたります。また、健診後には歯科衛生士によるブラッシング指導や生活習慣のアドバイスも行われます。
興味深いのは、企業によって健診の取り組み方に個性があることです。ある企業では、全社員対象に年1回の歯科健診を義務化しており、結果を健康管理システムに統合して健康経営の一環として運用しています。こうした取り組みが広がることで、「歯科=医療」から「歯科=予防・生活サポート」という新しい価値観が浸透してきています。
企業が歯科健診を導入するメリット
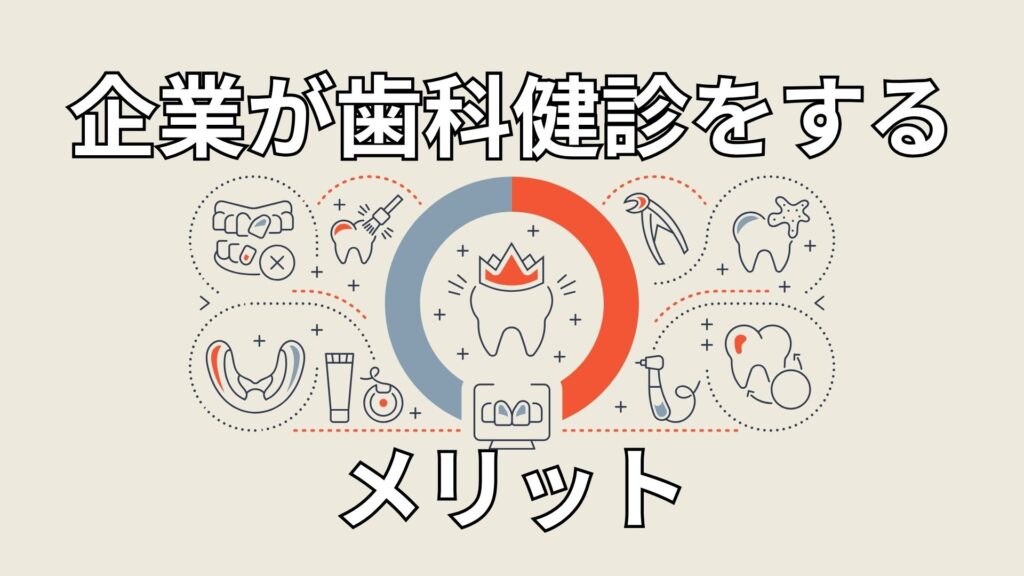
企業側にとって歯科健診を導入する最大のメリットは、「従業員の健康を守りながら生産性を上げられる」ことです。歯周病やむし歯を放置すると、痛みや不快感だけでなく、集中力の低下・欠勤・医療費の増加につながります。厚生労働省の調査では、歯周病が原因で年間に数百億円規模の労働損失が発生しているというデータもあります。
さらに、従業員が健康であることは企業ブランドにも直結します。「社員を大切にする会社」というイメージが強まり、採用活動にもプラスの影響を与えます。最近では「ホワイト企業認定」に歯科健診の実施を評価項目に加える動きも見られます。
歯科衛生士として現場に立つと、健診をきっかけに「歯医者って怖くないですね」と笑顔で話してくれる社員の方が増えるのを実感します。それが、企業にとっても社員にとっても、何よりの成果だと思います。
歯科衛生士の役割
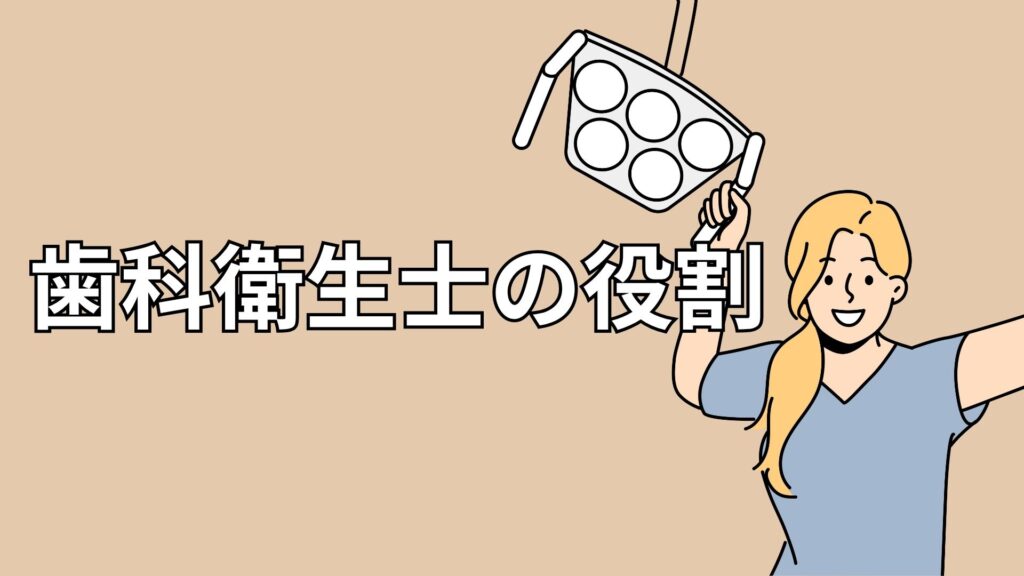
企業歯科健診において、歯科衛生士の役割は非常に大きいです。歯科医師が診断を行うのに対し、歯科衛生士は「予防とサポート」の専門家として、従業員一人ひとりの生活習慣に寄り添う立場にあります。
健診現場では、限られた時間の中で多くの従業員と接することになります。そのため、口腔内をチェックするだけでなく、「短時間で相手に気づきを与える力」が求められます。たとえば、「歯磨きはしているけれど、磨き残しがある部分がありますね」「デスクワーク中は口が乾きやすいので、水分をこまめに取りましょう」など、ちょっとしたアドバイスが大きな行動変化を生むことも少なくありません。
また、歯科衛生士は“話しかけやすい存在”であることも大切です。中には「歯医者が苦手でずっと行っていない」という人もいます。そんな方に対して、「無理せず、できることから始めましょう」と優しく声をかけることで、健診後に実際の受診につながるケースも多いのです。
歯科衛生士は単なる補助職ではなく、「健康意識の橋渡し役」。口腔ケアを通じて、社員一人ひとりの生活の質を底上げする存在であるといえます。
歯科健診でよく見られる口腔トラブル
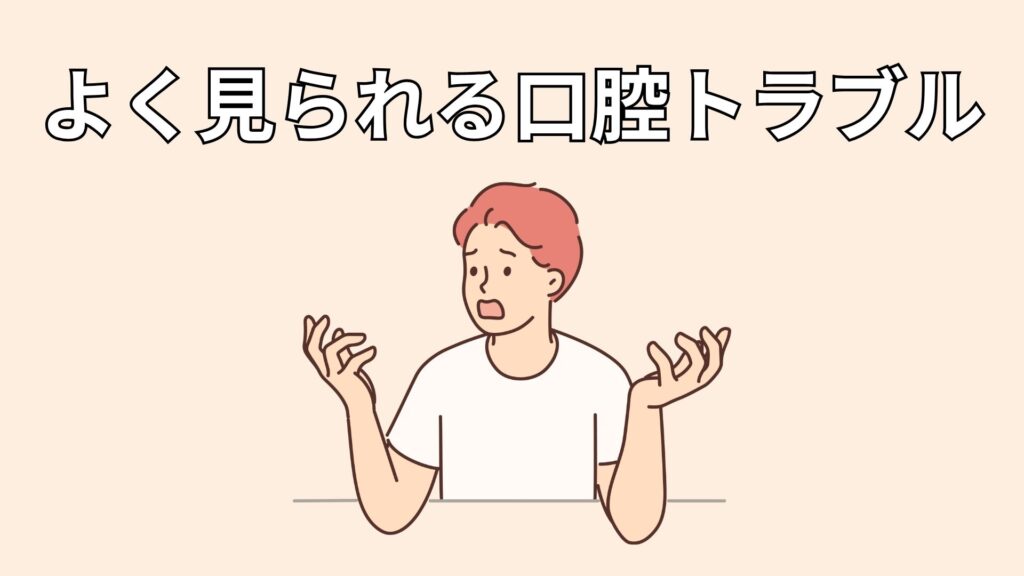
企業健診の現場で最も多く見られるのが「歯周病」です。実は、日本人の成人の約8割が歯周病予備軍ともいわれています。歯ぐきの腫れや出血があっても痛みが少ないため、放置してしまう人が非常に多いのです。しかし放っておくと、歯を支える骨が溶けてしまい、最終的には歯を失うことになります。
次に多いのが「むし歯」。特に働き盛りの30〜50代は、仕事のストレスや食生活の乱れによって、むし歯リスクが高まる傾向にあります。間食やエナジードリンクの常用、寝不足などがその一因です。
さらに近年増えているのが、「口臭」や「ドライマウス」といったトラブルです。会議や営業などで人と話す機会が多い職業の方ほど、口臭に敏感ですが、原因は口の乾燥や舌の汚れ、歯周病によるものなど多岐にわたります。
健診ではこれらの問題を早期に発見し、生活習慣の見直しを提案します。特に歯科衛生士が指導する「歯間ブラシ」や「フロス」の使い方を実践するだけでも、改善効果は大きいのです。
実際の企業健診の流れ

企業歯科健診の実施は、まず事前準備から始まります。健診ではまず、問診票をもとに日常のケア習慣を確認します。続いて歯科衛生士が歯ぐきの状態や磨き残しをチェックし、歯科医師がむし歯や歯周病の有無を診断します。
その後、歯科衛生士が個別にブラッシング指導を行います。ここで大切なのは、「押しつけないアドバイス」。たとえば、「忙しい中でも、昼食後だけは1分でも歯ブラシを当てましょう」など、現実的な提案をすることで、実践率がぐっと上がります。
最後に、健診結果をまとめた報告書を企業に提出し、必要があれば歯科医院での精密検査を勧めます。フォローアップとして健口セミナーの時間を設けるなどの企業も増えており、継続的なケア体制が整いつつあります。
働く世代の口腔環境の特徴

働く世代特有の口腔環境の変化では、30〜50代は責任の重い立場にあることが多く、ストレスや不規則な生活、睡眠不足が当たり前になっています。こうした生活リズムは、口腔内にも大きな影響を与えます。
ストレスが溜まると唾液の分泌量が減り、口の中が乾燥しやすくなります。唾液には自浄作用や抗菌作用があるため、分泌が減るとむし歯や歯周病のリスクが一気に高まります。また、夜遅い食事やアルコール摂取は口腔内環境を酸性に傾け、歯の再石灰化を妨げます。
さらに、喫煙は歯周病の最大のリスク要因のひとつ。歯ぐきへの血流を悪化させ、炎症を進行させてしまいます。職場での禁煙活動が進んでいるとはいえ、まだまだ口腔への影響を軽視している人も多いのが現状です。
歯科衛生士としては、こうした背景を理解した上で、一人ひとりに合ったアドバイスを行うことが大切です。
歯磨きは、「時間がない」「朝食を食べていない」といった理由で後回しにされがちです。しかし、少しの工夫で口腔環境を大きく改善することができます。歯科衛生士の立場から、簡単にできるケア方法をいくつか紹介します。
まず基本は「起床時の歯磨き」。わずか1〜2分でも構いません。ポイントは“歯ブラシを持つこと”そのもの。朝食を食べていないくても、寝ている間は唾液の分泌量が極端に減ることで、起床時には細菌が爆発的に増えます。忙しい朝は歯間ブラシやフロスを使うだけでも効果があります。
次におすすめなのが「水分補給」。長時間のデスクワークでは口が乾燥しやすく、口臭の原因にもなります。1時間に1回、コップ1杯の水を飲む習慣をつけるだけで、口腔内の環境が安定します。
また、仕事中の“ながらケア”も有効です。キシリトールガムを噛むことで唾液分泌が促進され、口臭予防や再石灰化を助けてくれます。
最後に、ストレスケアも忘れてはいけません。ストレスが強いと歯ぎしりや食いしばりを無意識にしてしまい、歯や顎に負担がかかります。深呼吸や軽いストレッチを取り入れることで、心と体、そして口の健康を保つことができます。
企業健診で見えてくる社会課題
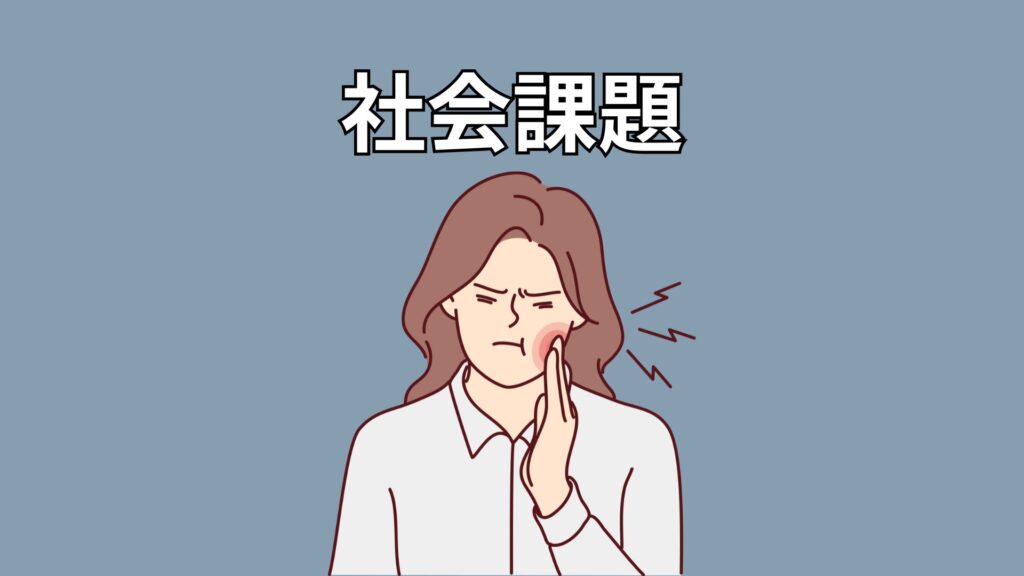
企業歯科健診の現場に立つと、「働く社会の縮図」が見えてきます。特に印象的なのは、口腔の不調がメンタル面に深く関わっているということ。歯の痛みや口臭は、自己肯定感を下げ、人とのコミュニケーションを避ける原因にもなります。
また、働き方改革が進む中で、「長時間労働」や「ストレス過多」といった課題も根強く残っています。これらは直接的に口腔環境を悪化させる要因であり、歯科衛生士としても無視できません。
さらに、非正規雇用やリモートワークなど働き方の多様化が進むことで、定期健診を受ける機会が減っている人も増えています。こうした人々にも歯科医療や予防情報が届く仕組みづくりが、今後の課題と言えるでしょう。
企業歯科健診は単なる福利厚生ではなく、「社会的予防医療の一環」です。従業員一人ひとりの健康を支えることは、ひいては企業の持続的成長、そして社会全体の幸福度向上にもつながります。
歯科衛生士が伝えたいメッセージ

歯科衛生士として最も伝えたいのは、「歯の健康=体の健康」だということです。歯周病は糖尿病や心疾患、認知症などとも深く関係していることが分かっています。つまり、口のケアは全身の健康を守る第一歩なのです。
そしてもう一つ大切なのが、「続けること」。健診で問題が見つかっても、改善のための行動を継続しなければ意味がありません。日々の小さな習慣、たとえば“寝る前の5分の丁寧な歯磨き”が、未来の笑顔をつくります。
歯科衛生士はそのサポート役として、「今できることから始めましょう」というメッセージを常に届けたいと思っています。完璧でなくても構いません。大切なのは、「自分の健康に関心を持つ」こと。その意識の芽が、人生を大きく変えていくのです。
まとめ

企業歯科健診は、単なる「歯の検査」ではなく、“働く人の健康と笑顔を支える大切な仕組み”です。
口腔の健康は、食事・会話・集中力など、私たちの生活の質すべてに関わっています。それにもかかわらず、忙しさを理由に後回しにされがちなのが現実です。
しかし、企業が主体的に歯科健診を導入することで、社員一人ひとりが自分の健康を見つめ直すきっかけになります。歯周病やむし歯の早期発見はもちろん、日常のちょっとした生活習慣の改善にもつながります。結果として、従業員のモチベーションや生産性が上がり、企業全体の活力にもつながるのです。
歯科衛生士として感じるのは、「予防」は決して特別なことではなく、“気づき”の積み重ねだということです。朝の歯磨き、水を飲む習慣、ストレスケア――こうした小さな習慣が、未来の健康をつくります。
これからの時代、歯科健診は「義務」ではなく「文化」として根付くことが理想です。歯を大切にする社会は人を大切にする社会となり、企業も個人も、共に笑顔で働ける環境を目指して、歯科衛生士としてそのお手伝いをしていきたいと思います。
ご興味のある企業様はこちらも合わせてご覧ください
【企業歯科健診】
