2025.09.29コラム
歯周病治療は痛い?歯科麻酔認定歯科衛生士が解説
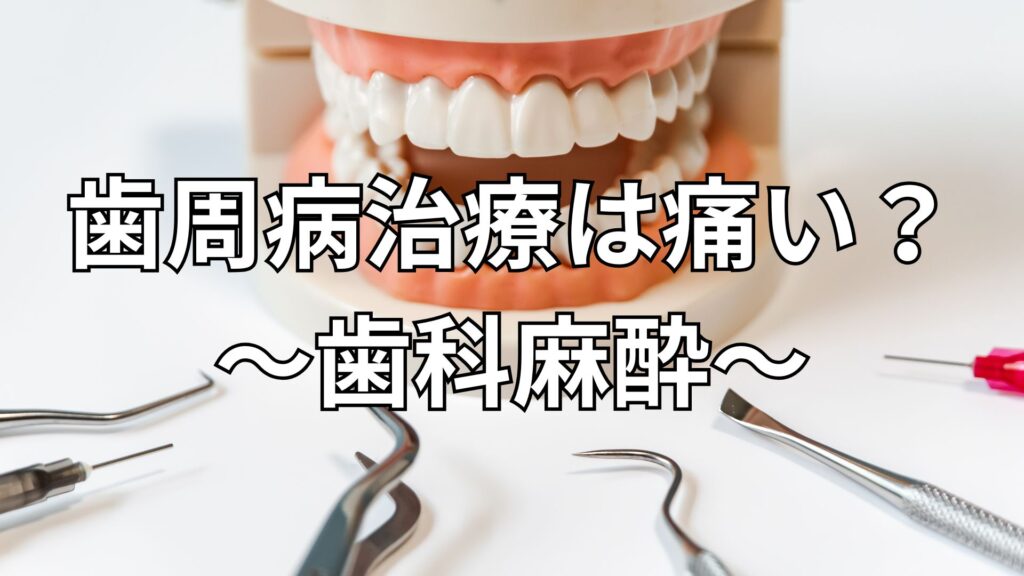
歯科医院に来られる患者さんの多くが口にする質問のひとつが「歯周病の治療って痛いんですか?」です。
痛みに対する不安が強いため、なかなか治療に踏み出せない方も少なくありません。
そこで今回は、歯科麻酔認定歯科衛生士の立場から、歯周病治療と痛みの関係についてわかりやすく解説します。
目次
歯周病とはどんな病気?

歯周病の進行段階
歯周病は、歯と歯ぐきの境目に細菌が繁殖することで炎症を起こし、歯を支える骨を徐々に破壊していく病気です。
初期段階では「歯肉炎」と呼ばれ、歯ぐきが赤く腫れる、歯みがきの時に血が出るなどの症状が見られます。
進行すると「歯周炎」となり、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、歯がぐらつき最終的には抜けてしまうこともあります。
初期症状と気づきにくさ
歯周病の厄介な点は、初期の段階ではほとんど痛みがないことです。
虫歯のように「ズキズキ痛む」という明確なサインが出にくいため、気づいた時にはかなり進行しているケースも珍しくありません。そのため、歯周病は「沈黙の病気」とも呼ばれています。
治療が必要な理由
歯周病を放置すると、口腔内だけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼします。糖尿病や心疾患、脳梗塞との関連性が指摘されており、近年では妊娠中の女性が歯周病にかかると早産のリスクが高まるとも言われています。
つまり、歯周病治療は「歯を守るため」だけでなく「体を守るため」にも必要不可欠なのです。
歯周病治療の基本的な流れ

①検査と診断
歯周病治療の第一歩は正しい診断です。歯科医院では、歯周ポケットの深さを測定したり、レントゲンで骨の状態を確認したりします。この段階では痛みはほとんどありません。
②スケーリング(歯石除去)
歯周病の原因であるプラークや歯石を専用の器具で取り除く処置を「スケーリング」と呼びます。軽度の場合はこの治療だけで炎症が改善されることもあります。チクチクする感覚やしみる感じが出る場合がありますが、耐えられないほどの痛みではありません。
そして、歯石の付着量が多く全て取ると痛みが出る可能性がある場合などは無理に取り切ることはせず、何回か回数を分けて取ることで歯がしみるなどの痛みを軽減できるようにします。
③ルートプレーニング(歯根の清掃)
歯ぐきの奥深くに入り込んだ歯石や細菌の毒素を取り除く治療です。
歯の表面を滑らかに仕上げることで、再び汚れが付きにくくなります。歯ぐきの中を触るため痛みが出やすく、この段階で局所麻酔を使用することが一般的です。
④外科処置が必要になる場合
進行した歯周病では、歯ぐきを切開して歯根や骨の状態を確認しながら清掃する「フラップ手術」が必要になることもあります。
外科処置と聞くと不安が大きいですが、しっかり麻酔を行うため処置中に強い痛みを感じることはほとんどありません。
歯周病治療は本当に痛いのか?

痛みの感じ方は人それぞれ
痛みの感じ方は個人差が大きく、「全然平気だった」という方もいれば「少ししみて辛かった」という方もいます。痛みに敏感な方は治療に対して恐怖心が強くなりがちですが、その不安を軽減するために麻酔が活用されます。
治療内容による痛みの違い
軽度のスケーリング程度であれば麻酔なしで行うことも多く、痛みはほとんどありません。
しかし、中等度以上の歯周病で歯ぐきの奥まで器具を入れる必要がある場合、痛みを避けるために局所麻酔を併用します。
外科処置になると、術中はしっかり麻酔でコントロールし、術後の痛みには痛み止めの内服で対応します。
麻酔を使うケースと使わないケース
患者さんの症状や痛みに対する不安の度合いによって麻酔の使用有無が決まります。
「痛みに弱い」「治療が怖い」という方は、遠慮なく麻酔を希望していただいて構いません。歯科麻酔認定歯科衛生士は、患者さんの気持ちに寄り添いながら安心できる環境を整える役割を担っています。
歯科麻酔の役割と種類

表面麻酔とは?
注射の前に歯ぐきの表面に塗る麻酔薬で、針の痛みを和らげるために使われます。ゼリーやスプレー状のものがあり、小児や注射が苦手な方にも有効です。
浸潤麻酔の仕組み
もっとも一般的な麻酔方法で、歯ぐきに少量の麻酔薬を注射して効果を得ます。治療する歯の周囲だけをピンポイントで麻酔できるため、歯周治療では主にこの方法が用いられます。
麻酔の効果と持続時間
麻酔の効き目は30分〜数時間ほど持続します。治療中はもちろん、治療後の痛みが出る前に処方される鎮痛薬を服用することで、強い痛みを回避できます。
歯周病治療の痛みを和らげる工夫
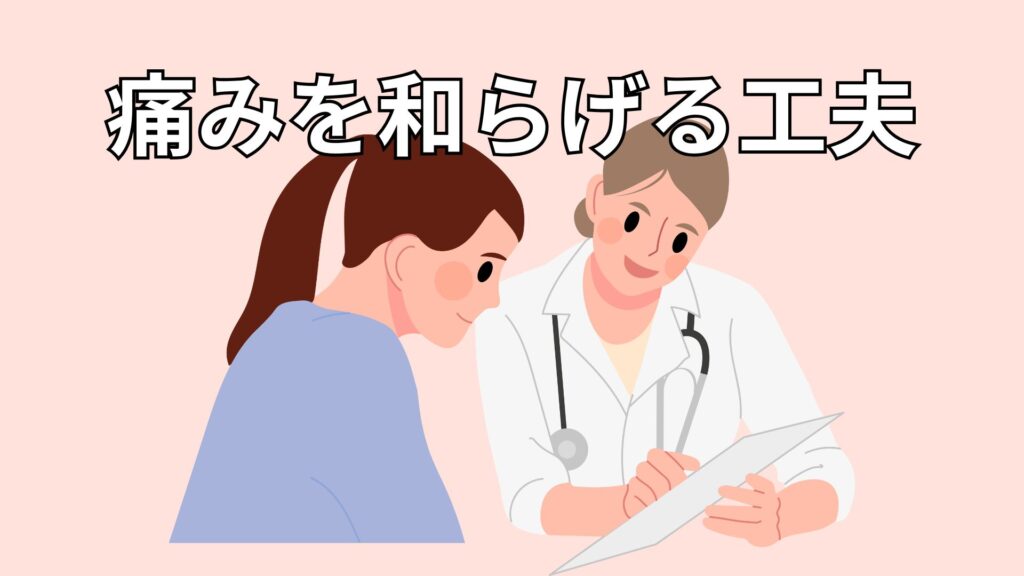
最新の麻酔技術
現在は極細の注射針や電動麻酔器を使用することで、注射そのものの痛みをほとんど感じないようになっています。従来の「チクッとする」感覚が苦手な方でも安心して受けられるように工夫されています。
歯科衛生士による声かけとサポート
処置中に「少しチクっとしますね」などの声かけを行うことで、不安を和らげることができます。人は先の見えないことに対して恐怖を感じやすいため、ちょっとした説明が痛みの感じ方に大きな影響を与えるのです。
治療後の痛みへの対処法
治療後は一時的に歯ぐきが腫れたり、しみたりすることがありますが、数日で落ち着くのが一般的ですが、歯ぐきの炎症が強く化膿している場合などは抗生物質を一緒に処方する場合があります。
処方された抗生物質や痛み止めを適切に使用し、無理に固いものを噛まないことで快適に過ごせます。
患者さん自身ができる準備
リラックスした状態で治療を受けることも痛みを和らげるポイントです。
前日はしっかり睡眠をとり、飲酒も控えていただくことをおすすめします。緊張しているときは深呼吸を意識するだけでも体は楽になります。
患者さんが安心して治療を受けるために

安全性を高める取り組み
「痛みを和らげる」ことに加えて、「安全に治療を進める」ことも当院が大切にしているポイントです。
麻酔の際にはパルスオキシメーターで血中酸素や脈拍をチェックしながら行うため、体調の変化を見逃すことはありません。こうした安全対策は、患者さんが安心して治療に集中できる大きな支えになっています。
「痛みの不安」を医療者に伝える大切さ
歯周病治療に対する不安の多くは「痛そう」「何をされるかわからない」という漠然とした気持ちから生まれます。そのため、治療を受ける前に「私は痛みに弱い」「麻酔をしてほしい」と伝えることはとても大切です。
歯科麻酔認定歯科衛生士をはじめとするスタッフは、患者さんの気持ちを尊重しながら治療計画を立てます。不安を隠さず話すことで、より安心して治療に臨むことができます。
コミュニケーションで痛みが変わる
人間は「予測できない痛み」に対して敏感に反応します。逆に「今から少しチクッとしますね」と説明を受けてから感じる痛みは、同じ強さであっても軽く感じる傾向があります。つまり、医療者とのコミュニケーションは、実際の痛みそのものを和らげる効果があるのです。
信頼できる歯科医院を見つけるポイント
「痛みに配慮してくれるかどうか」は歯科医院を選ぶうえで大切な基準のひとつです。
丁寧に説明してくれる、麻酔の種類や方法について相談できる、術後のフォローが手厚い──そんな歯科医院であれば、長期的に安心して通うことができます。
歯周病治療後の生活とセルフケア

治療後の過ごし方
歯周病治療の直後は歯ぐきが敏感になっています。刺激の強い食べ物(辛い物、熱い物、冷たい物)や、硬い物は避け、やわらかい食事を心がけると安心です。
また、出血がある場合は強くうがいをするとかえって治りが遅れることがあるため、優しくゆすぐ程度にとどめましょう。
自宅でできるケアのポイント
・正しい歯みがき:力を入れすぎず、歯ブラシを小刻みに動かす。
・補助用具の活用:歯間ブラシやデンタルフロスを併用すると効果的。
・定期的な洗口剤の使用:抗菌作用のある洗口剤でプラークの再付着を防ぐ。
これらを継続することで、再発を防ぎ、治療効果を長持ちさせることができます。
定期検診の重要性
歯周病は「治療して終わり」ではなく「継続的に管理する病気」です。数か月ごとのメインテナンスを続けることで、歯ぐきの健康を守り、再発を防ぐことができます。
まとめ
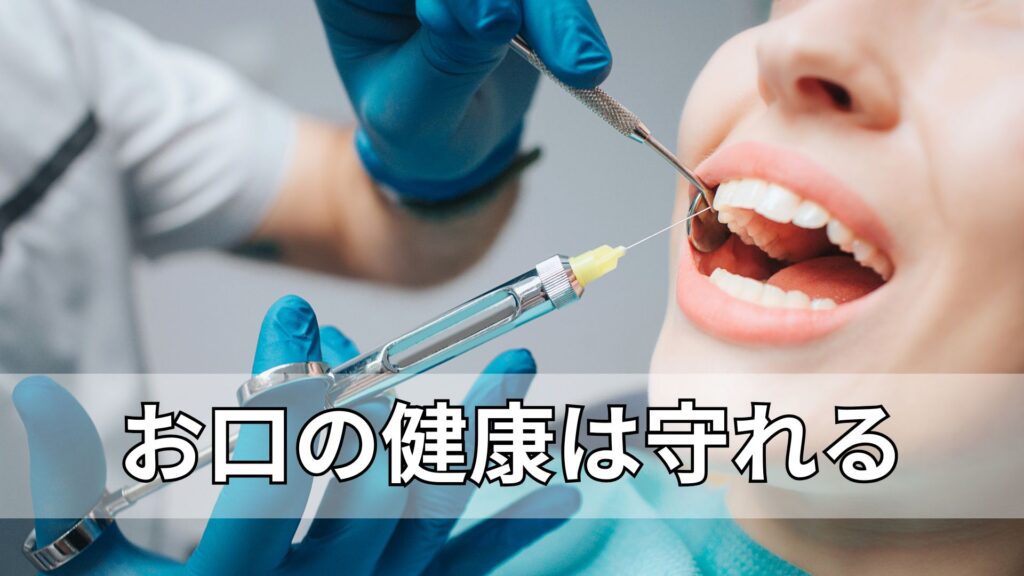
歯周病治療は、確かに処置の内容によっては痛みが伴うこともあります。しかし、現在では歯科麻酔の技術が進歩し、痛みを最小限に抑えながら治療することが可能になっています。さらに、歯科麻酔認定歯科衛生士が患者さんの気持ちに寄り添い、声かけやサポートを行うことで、安心して治療を受けられる環境が整っています。
「痛みが怖いから」と治療を先延ばしにしてしまうと、症状は悪化し、より大きな治療や抜歯が必要になることもあります。大切なのは、不安を一人で抱え込まず、歯科医院に相談することです。歯周病治療は「歯を守る治療」であり、「痛みをコントロールできる治療」でもあります。どうか安心して一歩を踏み出してみてください。
