2025.06.30コラム
放置しないで!「お口の老化」サイン今日からできる改善策
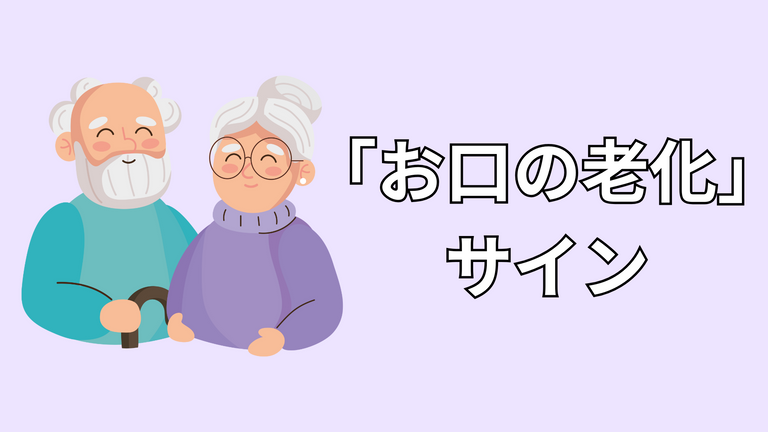
お口の健康は、全身の健康と密接に関係しており、中でも最近注目されているのが「口腔機能低下症」と呼ばれる病気です。歯が残っていても、「噛む」「飲み込む」「話す」などの機能がうまく働かなくなると、日常生活に大きな支障が出てしまいます。この症状を正しく理解し、早めにケアすることが、健康寿命を延ばすカギになります。
この記事では、西村歯科心斎橋診療所で勤務しております。口腔衛生部の叶より歯科衛生士の視点から、口腔機能低下症の基礎から予防法までを徹底的にご紹介していきます。
目次
口腔機能低下症とは?
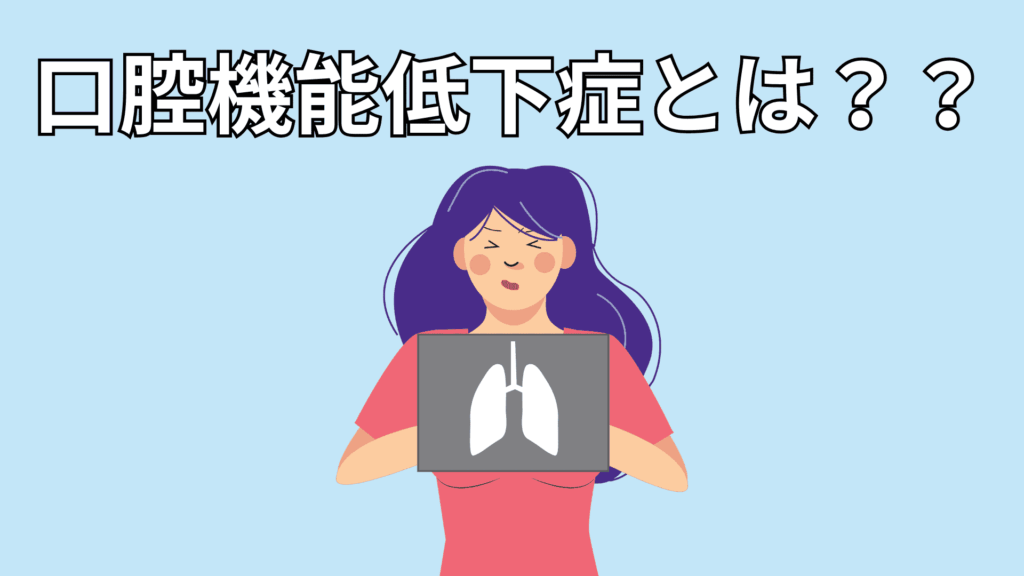
「口腔機能低下症(Oral Hypofunction)」とは、加齢や疾患などをきっかけに、口の機能が複数にわたり低下している状態を指します。たとえば、舌の動きが鈍くなる、食べ物をしっかり噛めない、飲み込むのが難しくなるなど、一つだけではなく複数の症状が絡み合って起こります。日本老年歯科医学会が提唱し、2018年に診断基準が定められて以来、保険診療でも扱われるようになりました。
この症状は、単なる「年齢のせい」ではありません。生活の質(QOL)を大きく下げるだけでなく、放置すれば誤嚥性肺炎や栄養失調、認知症のリスクまで高まってしまいます。だからこそ、早期の気づきと対策がとても大切です。
近年注目される理由
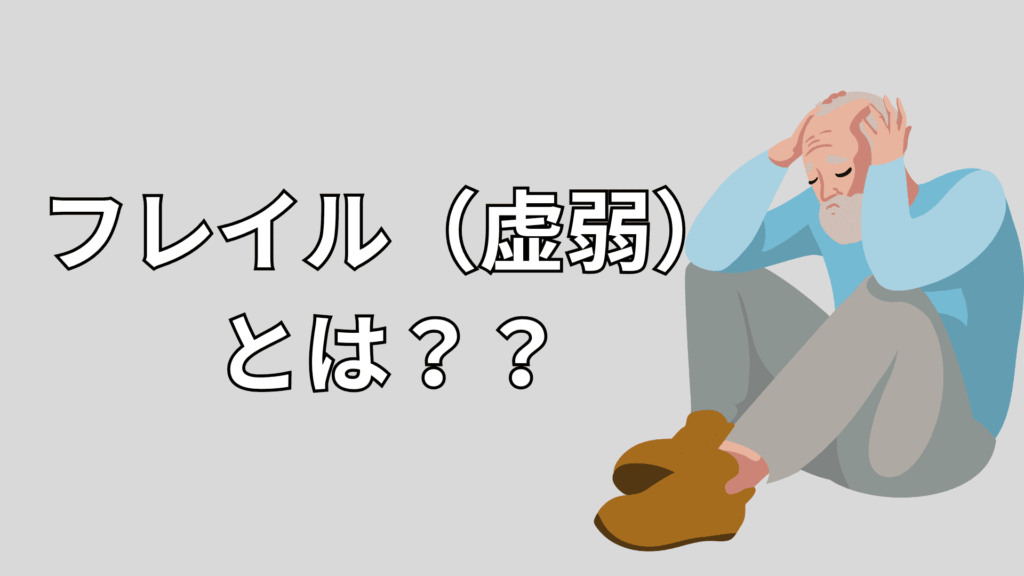
近年、この症状が注目されている背景には「高齢化社会」の進行があります。日本では、75歳以上の人口がどんどん増えている中で、見た目の歯の健康だけでなく、「機能的な健康」に焦点が当たるようになってきました。
また、健康寿命を延ばすための指標として、「フレイル(虚弱)」という概念が浸透していますが、口腔機能の低下は“オーラルフレイル”として、その前段階と位置づけられています。口腔機能をチェックすることが、全身のフレイル予防につながるという考え方が、医療・介護現場で広がっています。
「ちょっとした衰え」から始まる口の老化
オーラルフレイルとは、「加齢による口腔機能の軽度な衰え」を指す概念で、口腔機能低下症の前段階とも言われます。たとえば、「食べ物が口に残る」「滑舌が悪くなる」「食欲が落ちる」といった、普段生活していても見逃しがちな小さな変化がそのサインです。
この段階で気づいて対策を打てることができれば、口腔機能の回復や維持が十分に可能です。逆に放置すれば、全身のフレイル(虚弱)へと進行し、要介護状態になるリスクが一気に高まってしまうと言われています。
食べる・話す・呼吸する機能との関係
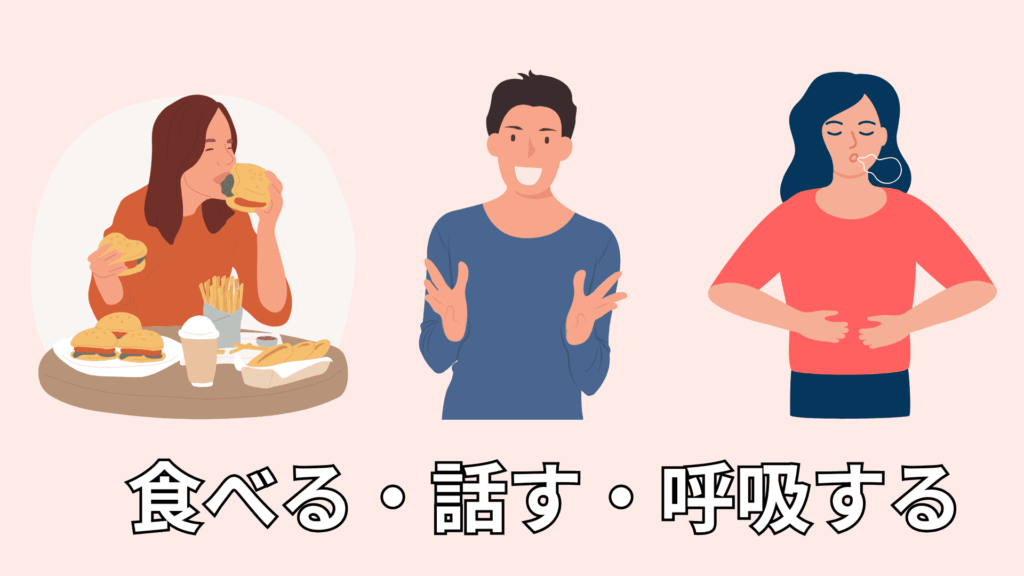
口は「食べる」だけじゃありません。話す・呼吸する・味わう・表情を作るなど、私たちの暮らしに欠かせない多機能な臓器です。これらが連動してうまく働いてこそ、食事も会話もスムーズに行うことができます。
たとえば、咀嚼力が低下すれば、食べられるものが限られて栄養バランスが崩れてしまう原因にもなりますし、発音が不明瞭になると、他人との会話が億劫になり、社会的孤立にもつながりかねません。さらに、口呼吸が常時行われるようになると、ウイルスや細菌に感染しやすくなるリスクも高まります。
健康寿命との関連性
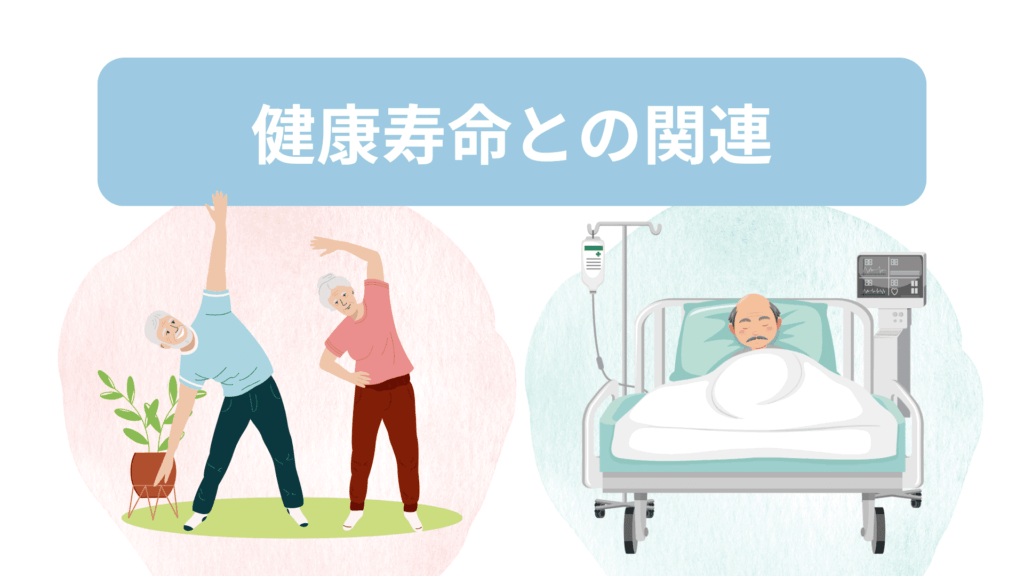
健康寿命とは、「介護を必要とせず、元気に日常生活を送れる期間」のことを指し、口腔機能の低下は、その健康寿命を縮める大きな要因の一つです。しっかり噛んで食べることで、脳への刺激が伝わり、認知症の予防にもつながることが分かっており、また、誤嚥による誤嚥性肺炎は高齢者の死亡原因の上位にあり、嚥下機能が落ちていると、食事中のむせ込みが起きやすくなり、そのまま命に関わるリスクも高まります。
だからこそ、口の機能を保つことは、単なる「歯のケア」ではなく、「人生の質を守る」ことに繋がってきます。
健康長寿のカギは“予防的口腔ケア”
オーラルフレイルは、生活習慣や日常の意識によって予防できます。とにかく大切なのは「気づいて早く動く」こと。少しでも違和感があれば、歯科医院での相談が第一歩になります。
口の衰えは、まさに“健康の入り口”です。毎日の食事や会話、笑顔のためにも、早期対策が欠かせません。
加齢による機能の衰え
年を重ねると、どうしても普段あまり使用していない筋力や神経の働きは落ちてきます。舌や口唇、頬の筋肉が弱くなることで、食べ物をうまくまとめられなくなったり、飲み込む力が落ちたりしてしまいます。
ただし、加齢だけが原因ではありません。同じ年齢でも口腔機能を保っている人もいれば、早くに衰えてしまう人もいます。その差を生むのは、生活習慣や意識の違いがあります。
保険適用で診断・指導が受けられる時代へ
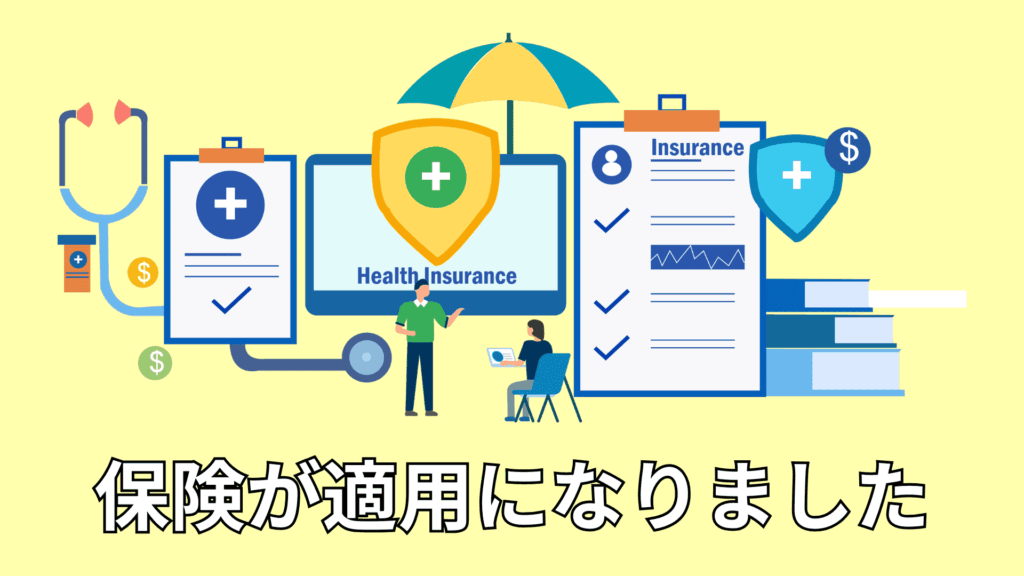
2018年から、一定の条件を満たせば「口腔機能低下症」が保険診療で評価・管理できるようになり、口腔機能の検査や評価、訓練が保険の範囲内で受けられるようになりました。対象年齢は、65歳以上で、7項目中3つ以上の機能低下が認められる場合になります。歯科医師による診断が必須ですが、歯科衛生士も連携して予防・管理を行っていきます。
嚥下障害、咀嚼力の低下などの兆候
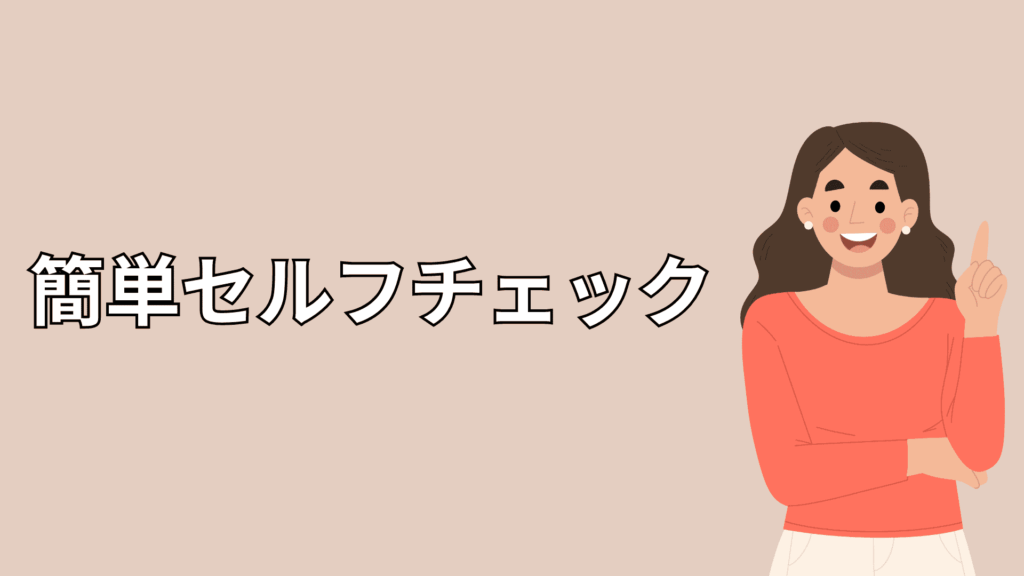
「最近、よくむせる」「固いものが食べにくくなった」「話すときに舌がもつれる」など、ちょっとした変化がサインです。他にも、「口が乾く」「口が開けづらい」「口臭が気になる」など、一見関係なさそうな症状も、口腔機能の低下に関係していることがあります。
簡単なセルフチェック方法
次のようなチェック項目を試してみてください。
・食事中にむせやすい
・硬い食べものを避けるようになった
・滑舌が悪くなったと感じる
・唇がよく乾く
・頬の内側をよく噛んでしまう
・食後に口の中に食べかすが残る
3つ以上当てはまる場合は、口腔機能低下症の可能性があります。歯科医院でのチェックをおすすめします。
歯科医院での診断と評価方法

歯科医院では、厚生労働省の基準に基づいた「7項目の検査」を通じて診断されます。具体的には以下の内容で行います。
1.口腔衛生状態(舌苔など)
2.口腔乾燥
3.咬合力
4.舌口唇運動機能
5.舌圧
6.咀嚼能力
7.嚥下機能
当院では、必要に応じてメンテナンスのタイミングでも実施することができますのでスタッフへお声かけください。
口腔機能訓練(オーラルリハビリテーション)

口腔機能低下症は、適切なトレーニングによって改善が期待できる症状です。歯科医院では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた「オーラルリハビリテーション」が行われます。これには以下のようなトレーニングが含まれます。
・舌の運動訓練:舌を左右・上下に動かしたり、頬を押したりして、舌筋を鍛える。
・口唇のトレーニング:パタカラ体操など、発音を利用して唇や頬の筋肉を強化する。
・咀嚼練習:柔らかいものから少しずつ噛みごたえのある食べ物へと移行して、噛む力を取り戻す。
これらは毎日続けることがポイントで、筋トレと同じように継続が成果を生みます。歯科衛生士がしっかりサポートしてくれるので、無理のない範囲で取り組めるよう指導してもらいましょう。
自宅でできる予防とケア
口腔機能低下症の予防には、日々のセルフケアが欠かせません。歯を磨くだけでなく、舌や頬、唇のストレッチを取り入れることで、筋力の維持につながります。以下はおすすめの自宅ケアの一例です。
・舌のストレッチ:舌をできるだけ前に出して10秒キープ、左右にも同様に動かす。
・口を「い・う」と大きく動かす体操:表情筋と口唇を動かす。
・ガムを使った咀嚼トレーニング:毎日5〜10分、左右の奥歯でバランスよく噛む。
これらはテレビを見ながらでもできる簡単な運動です。「ちょっとした習慣」が、数年後の大きな差に繋がってきます。
チェックして、相談して、始める!
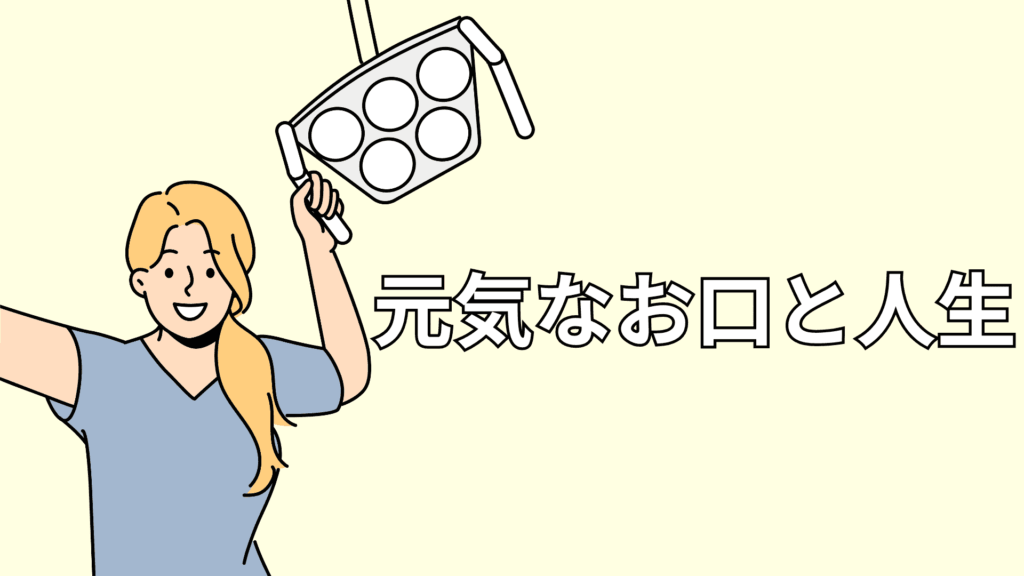
ここまで読んで「もしかして…」と感じた方、今が動き出すチャンスです。以下の3ステップで、今日から口腔機能改善を始めましょう。
1.セルフチェックをする:むせ、乾燥、噛みにくさを確認
2.歯科医院で検査を受ける:専門家に相談
3.自宅でケアを始める:舌トレ、ガム、食生活の見直し
「口が衰えると、心も衰える」と言われるほど、口腔機能は人生の質と直結しています。しかし、逆にいえば、口を元気に保てれば、心も体もずっと若くいられます。
そして、口腔機能低下症は、放っておくと食事・会話・健康寿命に大きな影響を及ぼす重大な症状です。しかし、早期に気づいて対策を始めれば、改善や予防が十分に可能です。
歯科衛生士はそのための強力なパートナーです。専門的なサポートと日々のケアで、元気な口と人生を取り戻し、ぜひ今日から口の健康を守る一歩を踏み出してみてください。
ご予約はこちらから
